本文
歴史民俗資料館だより【令和3(2021)年度】
3月号
あっという間に令和3年度も最後の月になりました。
弥生の始まりです。
今シーズンは、例年に比べて寒くて雪の多い冬でした。
寒さの残る資料館周辺の写真を紹介します(2月25日撮影)。

資料館東側の道路より

資料館裏手(2月25日撮影)
1枚目の写真のつららの下部分の植物です。

館前の杉浦翠子碑
春が待ち遠しい資料館周辺です。
2月号
年が明け、早くも如月がスタートしました。
今シーズンは日本全体で例年以上に寒い冬となっていますが、ここ軽井沢でも朝の冷え込みがマイナス二桁、日中最高気温がマイナスの日が頻発しています。
資料館では、先月、昨年開催した特別企画展「軽井沢のルーツを探る!~この土地に住んでいた縄文人とは?~」の展示解説パネルを軽井沢中学校に貸出し、展示をしていただきました。学校で勉強する歴史は、”教科書の中の話”という感覚で、あまり身近に感じることはないのではないかと思います。そのような中で、今回は中学生に地元の文化財・歴史について知ってもらう良い機会になりました。
中学校での展示の様子
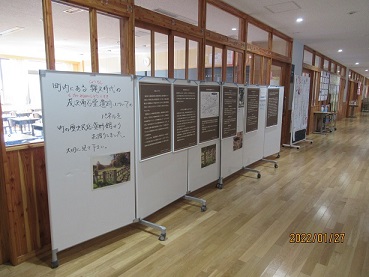
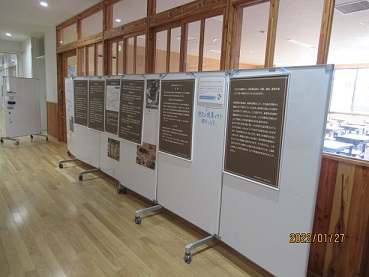

↑説明パネルを読んでくれています

↑土器を観察中です
一方で、新型コロナウイルス第6波の感染拡大により、予定していた小学生の社会科見学がキャンセルになってしまいました。子供達の学習の機会が失われてしまい、残念ではありますが、健康第一でなんとか乗り切っていきたいですね。
2022年 1月号
新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
12月半ば頃から、軽井沢でも雪が降り、寒い日が続いています。
現在冬期休館中の資料館と旧近衛文麿別荘(市村記念館)は、4月1日(金曜日)から開館します。皆様のお越しをお待ちしております。
館内展示紹介コーナー
冬期休館中ですので、今回は資料館・旧近衛文麿別荘(市村記念館)をそれぞれ紹介します。
資料館
2階の民具展示室では、昨年度に開催した「あつまれ!お話に出てくる道具たち」展のお話し紹介パネルを引続き設置しています。
この囲炉裏コーナーでは、ぶんぶく茶釜、さるかに合戦、一寸法師のお話を紹介していますが、他にも花咲じいさんやたぬきの糸車など多数紹介しています。

旧近衛文麿別荘(市村記念館)
旧近衛文麿別荘(市村記念館)は、実際に使用されていた別荘を移築したものです。
※詳しくはこちらをご覧ください。
1階は洋室、2階は和室があります。
館内を見学し、軽井沢の別荘建築を肌で感じてみてください。
1階

2階

12月号
師走となり、2021年もいよいよ最後の月です。
浅間山も雪が目立つようになってきました。
今年度の資料館・旧近衛文麿別荘(市村記念館)の開館期間は終了しました。
来年度は4月1日(金曜日)から開館しますので、皆様のお越しをお待ちしております。
※社会科見学を希望の学校は、ご連絡ください。
特別企画展関連 現地見学会 開催
11月6日(土曜日)、茂沢南石堂遺跡の見学会を行いました。
茂沢南石堂遺跡は、発掘調査後、一部がそのまま保管されており、町の指定文化財第一号になっています。柵の外から、石組石棺をはじめとした遺構を確認しました。
この日は快晴で、遺跡からは綺麗な浅間山を見ることが出来ました。
短い時間でしたが、文字のない縄文時代について、参加者の皆さんと思いを巡らす時間となりました。

文化講座「石仏散策のススメ~軽井沢の石仏調査を終えて~」開催
11月23日(火・祝)、令和元年度に教育委員会から出版された『軽井沢町石造物ガイドブック』の監修者である長野市立博物館学芸員の細井雄次郎氏に講師を務めていただき、開催しました。石仏の種類や調査の方法、町内の石造物と他地域の関連など、興味深いお話をたくさん聞くことが出来ました。

縄文土器の野焼き
11月27日(土曜日)、夏に開催した子供向けワークショップで作成した縄文土器の野焼きを行いました。
土器の急激な温度変化を避けるために、炎から離したところに土器をセットしてスタート。

土器の炎に当たる面をこまめに変えながら、徐々に炎に近付けていきます。

最後はこの状態に!

焼き上がりました。

当日は風が強かったため、火が安定せず予定より時間が掛りましたが、なんとか焼き上がりました。縄文時代の人々も、同じように苦労しながら縄文土器を焼き上げていたのかもしれません。今回の土器作りを通して、縄文人の技術力の高さを体感しました。
11月号
霜月が始まり、秋が深まってきました。
先月20日には浅間山の初冠雪がニュースになり、町内の木々も色付いています。

資料館入口(10月29日午前撮影)
文化講座「全盛期の縄文土器をよむ」開催
先月23日(土曜日)、現在開催中の特別企画展に関連した文化講座「全盛期の縄文土器をよむ」を開催しました。長野県立歴史館学芸員の水沢教子先生に講師を務めていただき、縄文時代の気候、人々の生活、土器の変化などについて最新研究の成果をお話しして頂きました。
参加した皆さんは、メモを取りながら熱心に先生の話に耳を傾けていました。今回は、嬉しいことに小学生も来てくれました。
最後の質疑応答ではいくつも質問が寄せられ、充実した文化講座となりました。

検温・手指の消毒等コロナ対策を行い、中軽井沢図書館 多目的室で開催
10月号
今年も残すところあと3か月、神無月に突入しました。
日に日に涼しくなり、空も秋の装いです。
今月は、現在開催中の特別企画展「軽井沢のルーツを探る!~この土地に住んでいた縄文人とは?~」に関連した文化講座を開催します。(長野県地域発元気づくり支援金活用事業)
とき 10月23日(土曜日)13時30分から15時まで
ところ 中軽井沢図書館 多目的室(衆院選選挙のため変更)
講師 水沢 教子 氏(長野県立歴史館学芸員)
題目 「全盛期の縄文土器をよむ」
定員 30名
対象 小学生以上
参加料 無料
申し込み 10月1日(金曜日)9時から電話・窓口で受付け開始
歴史民俗資料館 ☏0267-42-6334
※当日は、検温・手指の消毒・マスク着用・チェックシート記入にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染状況等により、中止となる場合があります。
館内展示紹介コーナー(不定期開催)
ツキノワグマの剥製(全長140センチ)です。
「にゃあ~」と鳴きだしそうで可愛くみえますが、鋭い爪が光っています。
今年5月には、資料館に隣接する離山公園内にクマが出現しました。来館者の皆様もご注意ください。

9月号
残暑から一転、半そででは肌寒い気候で長月の幕開けです。
長野県内でも、新型コロナウイルス感染が広がっています。
当館では、入口に、消毒液と来館者の氏名・連絡先・2週間以内の体調等を記入するチェックシートを設置し、検温を実施しています。また、使用スリッパやドア、手すり等の消毒も実施しています。
来館される皆様は、手指の消毒、チェックシート記入、検温、マスク着用の4点にご協力くださいますようお願いいたします。
お知らせ
下記の内容で予定していた歴史民俗資料館文化講座と特別企画展「軽井沢のルーツを探る!~この土地に住んでいた縄文人とは?~」現地見学会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となりました。
歴史民俗資料館文化講座
「石仏散策のススメ~軽井沢の石仏調査を終えて~」
とき 9月4日(土曜日)
講師 細井雄次郎氏(長野市立博物館学芸員)
(ホームページ「歴史民俗資料館 文化講座のお知らせ」ページに8月25日掲載済)
特別企画展「軽井沢のルーツを探る!~この土地に住んでいた縄文人とは?~」
現地見学会
とき 9月18日(土曜日)
集合 歴史民俗資料館
(ホームページ「歴史民俗資料館 特別企画展のお知らせ」ページ該当箇所に8月25日掲載済)
今後の開催については、決定次第ホームページでお知らせします。
ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
8月号
灼熱の暑さで葉月がスタートしました。
避暑地軽井沢でも、日中はエアコンが必要な暑さです。
資料館では、8月1日に特別企画展に関連した子供向けのワークショップを開催しました。
北相木村考古博物館学芸員の藤森英二先生に講師を務めていただき、粘土を使って土器を作りました!
最初に、縄文土器の基礎知識について説明を受けてから、作業をスタート!
粘土と砂を混ぜ合わせていきますが、この作業は思ったよりも力が要りました。その後、おせんべいのように丸く平らな底部分を作ってから、粘土を細長く伸ばしたものを底に沿って一段ずつ重ねていきます。重ねた後は、隙間が出来ないよう、外側からも内側からも粘土を伸ばして接着面を埋めていきます。
その作業を繰り返して高さが出たら、最後に貝殻や木のへら、撚った縄を使って装飾を施して、完成です!
しばらく乾燥させた後、秋に野焼きを予定しています。
縄文時代、土器は主に煮炊きの道具として使用されましたが、実際に作ってみると、当時の人々の技術力に驚きました。

藤森先生

立派な土器が出来ました!
7月号
下半期最初の月、文月が始まりました。
先月は、町内の小学校の6年生が見学に来てくれました!
これから歴史の学習が始まるという事で、みんな真剣に説明を聞いてメモを取っていました。6年生ともなると、興味のあることを自分なりに調べている子も多く、様々なことを質問してくれました。とてもユニークなものから、「確かにそうだね!」と納得するものまで!職員にとっては、色々な角度からの質問に気付かされることも多く、それが楽しみでもあります。
物心がついた頃から、スマートフォンやタブレット端末に囲まれていた子供達とのジェネレーションギャップに驚きながら、あっという間の1時間でした。
資料館見学が、歴史に興味を持つきっかけになれば幸いです。
6月号
あっという間に上半期最後の月、水無月になりました。
資料館では、5月15日(土曜日)と6月5日(土曜日)に盆栽講座と離山散策会を開催しました。
盆栽講座
ハンマーとみのを使って浅間石に穴を開け、そこに植物を植えて完成です。石によって固さが違うため、なかなか穴が掘れないものや、割れてしまうものもありましたが、参加者全員がオリジナルの盆栽を完成させることができました。


みんな頑張りました!
離山散策会
暑すぎず、寒すぎず、ちょうど良いお天気のなかで頂上まで登ってきました。この日はクマやイノシシとの遭遇もなく、ヘビさえ見かけませんでした。
植物園長の説明を聞きながら、3時間強で無事に下山してきました。



頂上:後方の浅間山は、雲に隠れていました

頂上:2036年に開封予定のタイムカプセル
5月号
皐月を迎え、木々が芽吹いてきた軽井沢です。
暖かくなってきましたが、資料館の敷地内では、未だに散ったさくらの花びらを見ることができます。

資料館 入口
旧近衛文麿別荘(市村記念館)が位置する離山公園内でも、段々と木々が芽吹いています。
風も爽やかで散歩が気持ちの良い季節になってきましたので、散歩を兼ねてお越しください。

旧近衛文麿別荘(市村記念館)
※5月上旬、この離山公園内にクマが出没しました。
資料館、旧近衛文麿別荘(市村記念館)へ来館の際はお気を付けください。
2021年4月号
令和3年度が始まりました。
資料館は、4月1日(木曜日)に開館しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引続き検温の実施や消毒液、チェックシートを設置しています。みなさまのご協力をお願いいたします。

例年に比べてとても暖かい日が続いている軽井沢ですが、木々の芽吹きの時期はまだ先です。





