本文
沿革
浅間根腰の三宿と呼ばれ・・・
追分の浅間神杜に、芭蕉の『ふきとばす石も浅間の野分かな』という句を記した碑があります。元禄元年(1688)、芭蕉は『更科紀行』の旅で中山道の追分・沓掛・軽井沢宿を通り、碓氷峠を越えています。当時3つの宿場は浅間根腰の三宿と呼ばれ、参勤交代の行列や善光寺参詣の人々でにぎわいました。いまその面影はほとんど失われましたが、追分にわずかばかり残る建築物が街道筋の風情を感じさせます。
明治になると離山から矢ケ崎を通り群馬県坂本へ通じる碓氷新道や馬車鉄道が開通し、近代化のなかで峠越えの旅は様相を変えていきます。

追分宿

沓掛宿

軽井沢宿

追分高札場

天保14年に建立された
『野ざらし紀行』の芭蕉句碑

旧三笠ホテル
屋根のない病院・・・
明治19年、一人の外国人の来訪が、軽井沢を宿場町から避暑地へと一変させます。友人とともに軽井沢を訪れたカナダ生まれの英国聖公会宣教師のアレキサンダー・クロフト・ショーは、すばらしい自然に感動して、『屋根のない病院』と軽井沢を称えました。明治21年には大塚山に山荘を構え、軽井沢の魅力を内外の知人に紹介。それ以後、別荘が建ち、明治中期には万平ホテル、三笠ホテルなどの西洋式ホテルが登場し、保健休養地としての地位を確立していきました
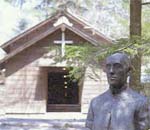
A・C・ショー氏記念碑とショー記念礼拝堂

軽井沢会テニスコート
(明治時代)

芭蕉句碑の回りに集まった人々
(明治25年頃)





