本文
令和5年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点について
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
また、個人住民税(町・県民税)における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
| 入居した年月 |
平成21年1月から |
平成26年4月から |
令和4年1月から |
|---|---|---|---|
| 控除限度額 |
A×5% |
A×7% |
A×5% |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで5年延長されました。
※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。
参考:厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金(注1)についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。
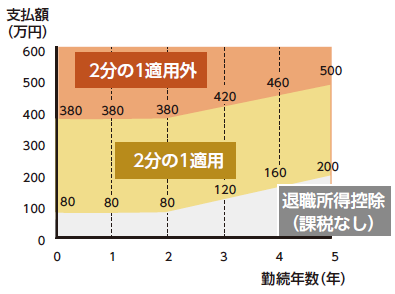
(財務省「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)パンフレット引用)
(注1)平成25年度分以降は、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しないことになっています。(平成24年度税制改正)
【参考】退職所得の課税方式(改正前)
他の所得と区分して次により分離課税
(収入-退職所得控除額(注2))×1/2日×税率(注3)=退職所得に係る町・県民税額
(注2)
- 勤続年数20年まで⇒1年につき40万円
- 勤続年数20年超⇒1年につき70万円
(注3)町民税6%、県民税4%
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。





